令和4年度3月【学校長の部屋】鴻池小
令和4年度 卒業証書授与式 式辞
令和5年3月20日(金曜)
校庭の木々のつぼみが、やわらかな春の光に包まれて少しずつふくらみを増してきました。この春の佳き日に、本校第40回卒業生として中学校へ巣立っていく103名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
只今、皆さん一人ひとりに卒業証書をお渡しいたしました。卒業証書を受け取る皆さんの姿は、希望に溢れキラキラと輝き、とても立派な姿でした。きっと皆さんの心の中には、入学の時から今日までの様々な思い出が、たくさん浮かんでいることと思います。
本日、ここに皆さんが6年間の小学校生活を見事に終え、このように素晴らしい卒業の日を迎えました。今日の卒業は、小学校生活を最後まで全力で頑張り通した結果です。皆さん全員が大いに胸を張ってください。
そして、この栄えある日に、ご臨席を賜りましたご来賓に皆様、ありがとうございます。心よりお礼申し上げます。
さて、卒業生の皆さんはこの6年間、鴻池小学校の児童として心も体も立派に成長を遂げ、学習や色々な活動を一生懸命やり遂げてくれました。特に6年生としての最後の一年間は、感染症対策で工夫した活動が求められる状況の中、「失敗を恐れず、『まずはやってみよう!』」を合言葉に、一人一人が自分で考え行動し、立派に最上級生としての役割を果たしてくれました。
広島・宮島への修学旅行では、「戦争の辛さを心に刻み 平和を願う」をスローガンに広島平和公園では、時間いっぱい活動に励みました。そして、広島での学びを下級生に伝える姿は六年生らしく堂々としたものでした。体育大会での全力疾走、笑顔と歓声、仲間と心を合わせた表現「僕らの夏だ」。皆さんの一生懸命な姿は、下級生や参観された保護者の心をうちました。日々の授業では、学習の見通しをたて、言語活動を大切にしながら、主体的に学ぶ姿が随所に見られました。授業に前向きにチャレンジする姿は、感動的で輝いていました。また、1年生との交流活動や2年生の九九検定など、下級生のことを気遣い、親切に接し、導いてくれ、最上級生として全校児童をリードしてくれました。様々な場面を振り返ったときに、自分の成長が実感できるはずです。大切なことは、頑張ってきた自分をちゃんと認めることです。頑張ればできるのです。それが自分への自信となるはずです。皆さんと過ごした思い出は、私にとっても決して忘れることできないものとなりました。校長として誇りに思います。
皆さんがこれから歩む人生は、決して楽しいことばかりではありません。幾多の困難や苦労が待ち受けているかもしれません。多くの困難や苦労を乗り越えて、はじめて立派な人となれるのです。人と人との絆を大切に、人の心を思いやる力、人の痛みを感じ取る力、人の命を大切にする力。そんな力を身につけ、現実と向き合ってください。
でも、幾多の困難や苦労に直面したとき、弱音を吐いてもいいのです。一人で何もかもできる人などいません。悩みを話し、苦しさを訴え、助けを求めましょう。
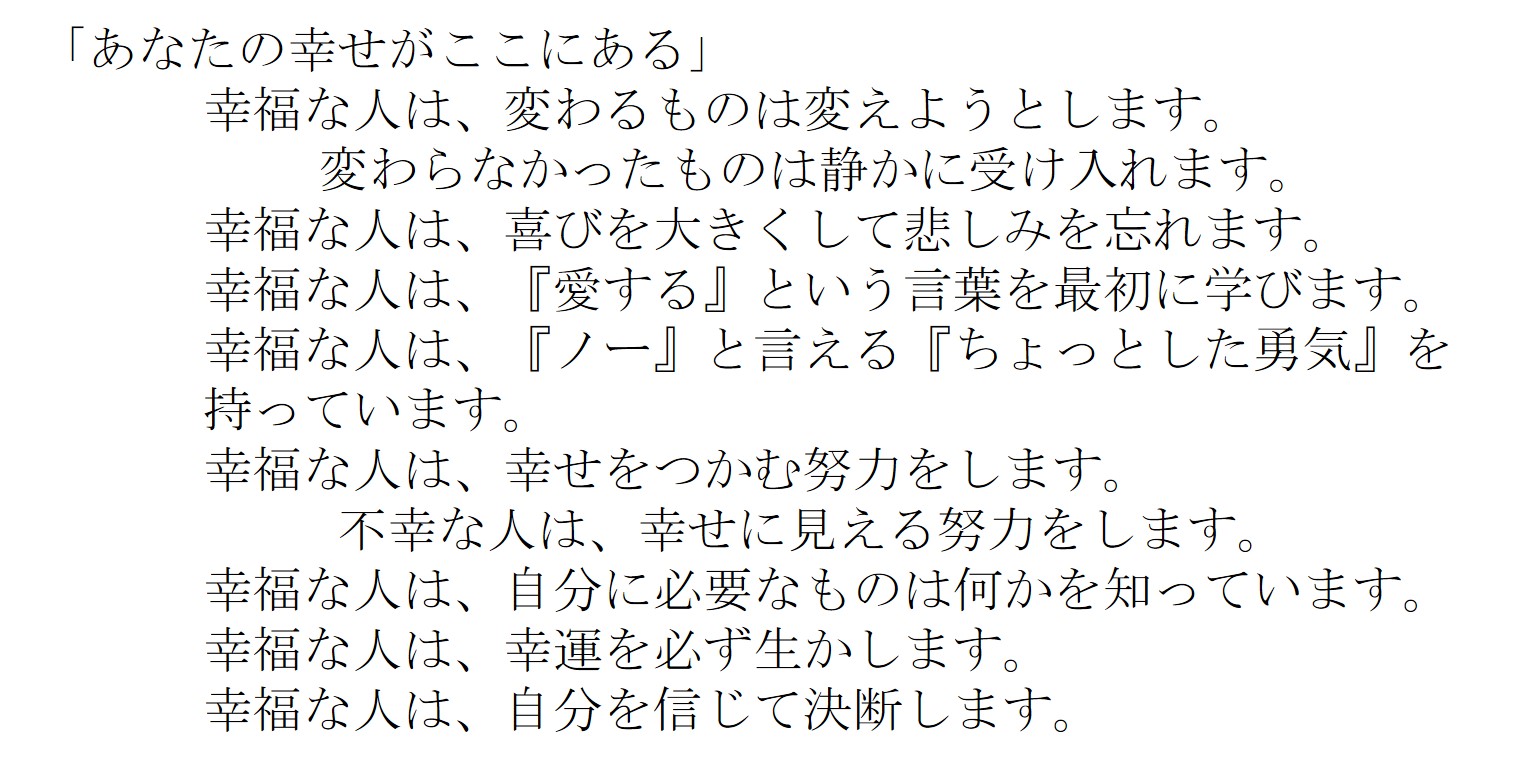
卒業する皆さんに、はなむけの詩を贈ります。アメリカのデニス・ウェイトリーの詩です。
この詩には、新しい世界で新たな挑戦をする皆さんが「幸せ」を掴むための八つのコツが示されています。皆さんが小学校において心がけやってきたこともありますが、まだできなかったこともあると思います。特に後半の「幸せに見える努力でなく、幸せをつかむ努力をする」「自分に必要なものは何かを知る」「幸運を必ず生かす」「自分を信じて決断する」という四つは、これから新たな挑戦を始めようとする皆さんにとって、今後の取り組みの在り方を示すものです。是非、これから始まる新たな世界を存分に楽しんでください。
最後になりましたが、保護者の皆様、お子様のご卒業、誠におめでとうございます。教職員一同心よりお祝い申し上げます。子どもたちは、人生において最も多感な時期に入ります。楽しみの多い反面、保護者として悩むことも多いかと存じます。しかし、皆様の前向きに生きる姿が、必ず子どもたちを勇気づけます。子どもたちが「夢」に向かう姿をどうぞ温かく見守り支えてあげてください。家族の温かい支えが子どもたちの成長には欠かせない大きな力となります。
私たち教職員一同、お子様の学校生活が豊かなものになるよう、一致団結して寄り添ってまいりました。しかし、ご心配やご迷惑をおかけしたことも多々あったのではないかと思います。それでも、お子様たちは優しく、逞しく成長し、今日の日を迎えることができました。これもひとえに保護者の皆様方の、ご理解とご協力があったおかげと深く感謝しております。
今後とも、信頼される学校づくりを目指し、教職員一同努力してまいりますので、これからも一層のご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。
では、卒業生の皆さん、健康に十分注意して、鴻池小学校での六年間を誇りと自信とし、大いに活躍されますよう、心よりお祈りして、私の式辞といたします。
「授業研究」と「研究授業」
令和5年3月15日(水曜)
3月2日の校内研究会でも話題となったことですが、改めて「授業研究」と「研究授業」の違いについて少し触れておきます。「授業研究」は、「公開授業」や「研究授業」という形で行われます。「公開授業」とは、文字通り授業を自分以外の誰かに見せることです。「公開授業」は、授業を他人に見せることにより、「自らの気づき」によって授業改善、指導力の向上を図ります。「研究授業」は、よりよい授業のあり方を求めて、研究的、実験的に行う授業のことをいいます。学校や研究機関から与えられたテーマに基づいて授業が作られ、その授業を同僚や学外の参観者に見せ、指導・助言を受け、授業の改善に資しようとして行う授業のことをいいます。「研究授業」を行うことにより、「組織としての気づき」によって授業の改善、指導力の向上を図るものです。「研究授業」を通して、よりよい授業のあり方を研究することを「授業研究」といい、組織的・計画的に取り組まれています。「授業研究」をする目的には、2つあります。一つは、子どもたちの学力を高めることを目的とした授業づくりが進みます。もう一つは、「授業研究」をすることによって、授業をする教師の授業力が高まります。さらには、「個人の力」を高めるとともに「個人間のつながり」を生み出し、チームとしての力を高めることにもつながります。「授業研究」とは、教員が一人で行う授業準備のための研究ではなく、学校組織として授業を公開し、その後に行う事後研究会をも含めた取り組みのことをいいます。学校は、教師が専門家として学び、成長し合う場所でなければなりません。
教師は学校で育ちます。子どもたちの「学び」と、教師の「学び」が尊重される文化を持つ学校で育ちます。教師は「教える専門家」であると同時に「学びの専門家」として、「学ぶこと」が何よりも重視される環境づくりに努めていかなければいけません。保護者から子どもを通わせたいと思う学校をつくる、それが「学びの共同体」づくりです。
校内研究のすすめ
令和5年3月7日(火曜)
3月2日、大阪大谷大学教育学部教授 今宮伸吾先生を迎えて校内研究会を実施しました。研究会では、今年度の校内研究の成果と課題をもとに、来年度の研究の方向性について、今宮先生からアドバイスをいただきながら協議しました。本校では、『自ら考え、表現する子の育成』を研究主題に、学校教育目標の達成に向けて各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、教育の内容を組織的に配列していく教科横断的な単元づくりに取り組んできました。特に『課題設定、話し合い活動、ふりかえりの充実』を共通実践項目として子どもたちのために何ができるか、何をすれば子どもたちの学力の向上につながるかを意識して取り組んできたところです。子どもたちの活動を重視し、一時間ごとに学習のねらいを明示し、見通しをもって課題発見・解決に取り組ませました。また、学習に対するふりかえりを行い、次時の学習につなげていくなど、探求的な学習にも取り組みを広げていきました。その取り組みを通して見えてきた成果は、めあてを意識し、見通しを持って学習に取り組み「自ら学ぶ姿勢」が見られるようになってきました。また、話し合い活動では、国語科で学んだ「話し方」、「聞き方」、「話し合い」等、他の教科でも生かすことができるようになってきました。課題としては、「まだまだ表現力や語彙力に個人差がある」や「自分の思いを発表できるようになってきたが、他者の考えを聞く姿勢に課題がある」といったことが見えてきました。成果と課題を踏まえ、来年度の研究の方向性としては、まだまだ課題が残るところが大きいということで引き続き研究主題を「自ら考え、表現する子の育成」としました。また、副題については、「課題設定、ふりかえりの充実を通して」とし、ゴールを意識した活動を行うことで意欲を持たせ、次時の学習につながる探求的な学習に取り組むことができると考えます。また、児童理解のための手段として「学級力向上プロジェクト」も引き続き取り組身、安心して学べる場づくりに取り組みます。取り組む内容はこれまでと大きく変わるものではありませんが、明らかとなった課題を克服するために、次の3点を重点的に取り組むこととします。1「主体的に学習に取り組む態度」を育むために、教師と子どもにとっての意味ある「ふりかえり」の充実を図ります。また課題設定にあたっては、生活実態に合った課題を設定し、単元全体を見通して、ゴールを意識した授業をデザインしていきます。2「個別最適な学び」の一層の充実を図ります。一人一台のタブレットの活用について、授業場面の設定に応じた対応を図るなど、効果的なタブレットの活用場面を工夫していきます。また、子ども一人一人の育ちが明確になるようめあてに沿った視点を示すなどルーブリック評価を実施していきます。3「ピア学習の成立(協働的な学び)」学習者同士の協働的な学びの時間を大事に、共創意識を高めていきます。以上の3点を重点的に取り組むとともに、学校教育目標の具現化に向けてカリキュラム・マネジメントを基盤に3つの側面の一つ、教科等横断的な視点での教育課程を編成します。教育課程を構成するすべての教科がそれぞれの役割を果たすと同時に、国語科で養った言語能力を他の教科でも育成するような教科をまたいだ教育課程の編成が求められています。二つ目の側面は、PDCAサイクル(計画,実施,評価,改善)の確立です。学校教育の効果を学校教育目標や目指す子ども像に沿って常に検証して改善していきます。最後に三つ目の側面、地域と連携し、よりよい学校教育をめざします。教育課程の実施に必要な人的または物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことです。これらカリキュラム・マネジメントの3つの側面を通して、教育課程に基づいた教育活動を行い、子どもたちの資質・能力を育成していきます。まずは、教師間の「めざす子ども像」の共有が必須となります。
学校におけるすべての教育活動は、学校の教育目標の具現化を目指す意図的な営みです。したがって、校内研究もまた、学校の教育目標を達成するためにどうすればよいかを全教師で追究する研究活動であると捉えることが大切です。
2022年度「お別れ遠足」

令和5年3月1日(水曜)
卒業まで登校日数も2週間あまりとなりました。6年生みんなで最後の思い出をつくろうと、2月28日に「ひらかたパーク」へお別れ遠足に行ってきました。私が6年生を担任していた頃(約20年以上前)は、今はもうありませんが、宝塚のチボリのスケート場や阪神パークのスケート場、須磨の水族館、エキスポランド(万博公園)などに子どもたちと一緒に行ったものです。校長になってからも、これで10回目のお別れ遠足に引率することになります。ユニバーサルスタジオジャパンをはじめ姫路セントラルパーク、キッザニア甲子園、そして今回、子どもたちと一緒に行った「ひらかたパーク」。ちなみに、お別れ遠足の行き先については、子どもたちのプレゼンテーションによって決めたようです。以前であれば、先生が「どこにお別れ遠足に行く」と決めていたものですが、これも時代の流れでしょうか。子どもたちが主体となって行き先を決定しているようです。ただし、何でもいいというわけではありません。条件をつけて決定しています。今回も、京都水族館やネスタリゾート神戸、姫路セントラルパーク、琵琶湖博物館など、それぞれのテーマパークのアトラクションの数や面白さ、その場所自体の面白さ、そしてかかる費用まで、子どもたちが熱心にプレゼンをして決めています。子どもたちのプレゼン能力に圧倒されることもしばしばです。でも、どの場所に決まっても子どもたちにとっては、思い出に残るお別れ遠足になっています。時期もあるのですが、どこに行っても同じようにお別れ遠足に来ている学校がたくさんあり、今回のお別れ遠足にもたくさんの学校が来ていました。アトラクションには子どもたちの行列が、うちの学校の子どもたちがどこにいるのか探すのも一苦労。交通事情もあり、10時の開園に間に合わなかったのですが、フリーパス券を手に巻いて「いざ出発!」。元気よく遊園地に散らばっていきました。レッドファルコン(ジェットコースター)、お化け屋敷に行くグループ、垂直降下する超絶叫マシン(メテオ)をお目当てに行ったら点検中で乗れなかったり、絶叫系の乗り物は苦手な子どもたちのグループは、かわいらしい乗り物で楽しんだりと、それぞれが午後2時の集合時間のギリギリまで、いろいろな乗り物に乗りに乗って、楽しそうな笑顔がいっぱいでした。楽しいひとときは、あっという間に過ぎていき、気がつけば集合の時間です。卒業まであとわずかですが、思い出に残る一日になったことと思います。







更新日:2023年03月22日