令和4年度12月【学校長の部屋】鴻池小
2学期終業式
令和4年12月23日(金曜)
長い2学期も、今日が最後の登校日。ゴールの終業式を迎えることができました。合言葉、失敗を恐れず「まずは、やってみよう」で2学期を乗り越えてきました。まだまだ暑さが残る2学期の始業式に3つのお願いをしました。一つ目は「新型コロナウイルスや熱中症に十分気をつけて生活しましょう」でした。二つ目は「友だちや下級生から必要とされる人になりましょう」。そして、三つ目が「学習や行事に『本気』で頑張りましょう」の3つです。
2学期は、新型コロナウイルスや熱中症に十分気をつけて生活ができたからこそ、体育大会や遠足、学習活動を中止や延期することなく実施できました。子どもたちが感染防止や熱中症に取り組んでくれたお陰です。二つ目は「友だちや下級生から必要とされる人になりましょう」でした。一生懸命廊下に雑巾がけを頑張った子、隅々まできれいにしようとする姿や、毎日みんなが使って汚れているところを丁寧に掃除する姿が見られました。6年生は1年生に、5年生は3年生に、4年生は2年生に、下の学年の子が喜んでもらえるよう交流会を企画し、下の学年の子に優しく接していました。そして、5年生は「未来に目を向けようSDGsプロジェクト」をテーマに「服の力プロジェクト」を実施しました。世界に住む難民のために、保護者や地域、幼稚園に中学校にまで協力を求めて取り組み、2144枚の服を難民の子どもたちに送ることができました。鴻池小学校の子どもたちが、友だちのため、下の学年の子のため、もっといえば、様々な人のために頑張った2学期になりました。三つ目の「『本気』で頑張る」です。6年生の体育大会、表現「僕らの夏だ」では、みんなで協力し合い、最後の体育大会を全力で楽しもう」をスローガンに本気で頑張りました。「さすが6年生」を感じさせられる素晴らしい演技でした。見ていた1年生から5年生が、6年生になったらあんな演技をしてみたいと感じたことでしょう。その他の学年の子どもたちも、全力で走りきった学級全員リレー、そして、一人一人が演じきった表現、どれも「やってやる」を感じさせる素晴らしいものになりました。これからは、「やればできる」を自信に変えてください。子どもたちが掃除や給食当番の仕事、係や委員会の仕事など、人のために、今、自分ができることを精一杯取り組む姿をたくさん見ることができた2学期でした。どの子も、毎日一生懸命こつこつ取り組む「本気」の姿を見ることができて大変うれしく思います。
さて24日(土曜)からは、17日間の冬休みです。感染症や交通事故には十分注意して、楽しく有意義な冬休みにして下さい。そして、1月10日(火曜)に2023年の新たな目標をもった皆さんと会えることを、校長先生、そして担任の先生、鴻池小学校の全ての先生方が楽しみにしています。それでは,楽しい冬休みにして下さい。
『運』を呼び込んでください!
令和4年12月22日(木曜)
毎朝のことですが、下足室で子どもたちをまずは出迎えています。7時55分になるまでのほんの数分ですが、子どもたちとの会話を楽しんでいます。「今日は、何の日」と子どもたちに尋ねると、子どもたちから返ってきた答えは「お楽しみ会の日」。なるほど、明日は終業式、みんなで2学期頑張ってきたことをねぎらい「お楽しみ会」なんですね。そう返してきた子どもたちに、「今日は『冬至』だよ」と返すと、きょとんした顔。「1年で最も昼の、太陽の出ている時間が短い日だよ」と教えてあげたら、「へぇーそんなんだ」と納得顔。ちょっとした子どもとの会話を楽しんでいます。
さて、今日は、冬至です。冬至は、別名「一陽来復」といわれます。意味は、「冬が終わり、春が来ること、新年が来ること」や「悪いことが続いた後で幸運に向かうこと」という意味があります。太陽の力が一番弱まった日であり、この日を境に再び力が甦ってくるという前向きな意味合いを含んだ言葉でもあります。かぼちゃを食べて栄養を付け、身体を温めるゆず湯に入り無病息災を願いながら寒い冬を乗りきる知恵とされています。
カボチャには、ビタミンが多く含まれているので、寒さが厳しくなるこの時期に食べると、かぜにかかりにくくなる効果があるといわれています。また、カボチャは、「なんきん」とも言います。名前に「ん」のつく食べ物を食べると「運」を呼び込むという言い伝えがあります。他にも、「ん」がつく食べ物には、蓮根(れんこん)、人参(にんじん)、銀杏(ぎんなん)、金柑(きんかん)、寒天(かんてん)、饂飩(うんどん)などがあります。これは「冬至の七草」と呼ばれるものです。「いろはにほへと」が「ん」で終わるように、「ん」には一陽来復の願いが込められているのです。「ん」のつくものをたくさん食べて「運」を呼び込んでください!
デジタルドリルの活用

令和4年12月21日(水曜)
AI技術を活用し、子どもたちの学習状況に応じた学習支援や個別最適化された問題を自動で出題することができる機能を有した「ミライシード」が12月から市内一斉に導入されました。本校では、12月の期間をお試し期間として、3学期から本格的に活用していくこととしています。
「ミライシード」の機能の一つに「ドリルパーク」があります。「ドリルパーク」は、個々の子どもの学習到達度や学習のペースに合わせて取り組める個別学習ドリルで学習内容を定着させ、理解をさらに深めることができます。本校のICT担当教諭によれば、今の「ドリルパーク」の活用の状況について、活用が始まって2週間ですが、いくつかの課題があることがわかりました。まず一つ目は、「ポイント稼ぎをする子が現れる」ということです。児童の意欲を向上するために、取り組み数や連続正解数などでポイントやメダルが獲得できる仕組みになっています。同じ問題を何度解いてもポイントが得られるため、ポイント欲しさに同じ問題を、答えを覚えて解く子がいるようです。二つ目は、「解き直しへの意欲の差がある」ということです。ICT担当教諭のクラスでは、宿題として活用し始めています。取り組みの様子を確認していると、正答率が100%になるまで何度も間違った問題を解き直す子もいれば、2~3分でさっさと取り組み、0%のまま終える子もいるようです。教諭は、「宿題として活用し、意味のあるものにするためには、取り組む基準を設定する必要があるかもしれません」と分析しています。さらには、「正答率70%を超えるまで最低10回は取り組む」や「10回取り組んでも超えない場合は苦手なので、学校で一緒に先生と復習しよう」と、ただ活用させるだけではなく、教師の取り組み方にも言及しています。
1人1台端末の活用においては、自治体や学校によって、デジタルドリルを導入が進められています。文科省は、デジタルドリルの活用について「児童生徒の実態に応じた適切な使用を行うことができれば、子どもの学習状況や進捗状況の把握を行うことが容易になり、補充的・発展的な学習を行う場面等において、個別の学習支援を行いやすくなると考えられる」としています。また、「子ども自身がスムーズに解けた得意な問題やつまずきのあった苦手な問題を把握し、学習の改善につなげる活用も期待できる」とも、デジタルドリルに対する考えを示しています。
デジタルドリルの機能には、教師が1時間の授業で達成させたい目安となる問題を子どもたちに配信し、自動採点機能により、問題に正解すると、より発展的な内容の問題に取り組むことができ、誤答があった場合は、その内容に即して補充的な問題が出されます。システムが正誤の判断によって、より難易度の高い問題を出したり、間違いを重ねることでシステムがつまずきの原因を特定し、それを解決するための新たな問題や解説が表示されたりします。そうした機能を生かしながら、子どものそれぞれの実態に応じた学習が進められるようになります。朝学習や放課後学習や、自宅での家庭学習に活用するなど、子ども自身が学習の進め方を考えることも含め、指導の効果が高まるように工夫を考えていく必要があります。
いじめ問題を考える
令和4年12月8日(木曜)
平成 25 年に施行された「いじめ防止対策推進法」では、いじめの定義について「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない」としています。被害を受けた子どもの心や体に苦しさや痛みを感じたらいじめということになります。子どもたちが「ふざけ」として行った行為であっても、被害を受けた子どもが「嫌だ」「つらい」「やめてほしい」と感じていたら、その行為は「いじめ」になると法律で定めているのです。
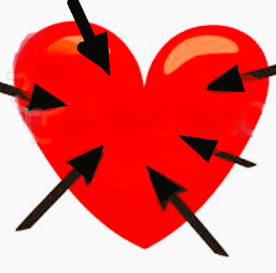
なぜ、いじめがなくならないのでしょうか。2021年度のいじめの認知件数は、小学校で50万件を超えて、過去最高でした。また、いじめが原因で自殺する人も減っていません。いじめは、友だちが失敗をしたり、人と違っていることを笑ったりすることもいじめです。他には、「ねえ、ねえ ○○ちゃんと話すのやめよ」とその人が来たら急におしゃべりをやめたり、逃げたり、ひとりぼっちにしたり、遊ぶふりをして、たたいたり、けったりする暴力、これもいじめです。友だちのものを盗ったり、隠したりすることもいじめです。スマホやタブレットを使って「○○うざい、まじ学校に来んな」など、ネット上への書き込みをすることもいじめです。まだまだあります。これらのいじめの行為が心にいじめの矢となって突き刺さります。
いじめをした多くの子が、「悪気はなかった」「そんなつもりじゃなかった」といいます。私たちはみんな違っていていいのに、比べたり裏切ったり、人間としてとても醜い心が時々顔を出します。私たちは、お互いにここに存在する事実に感謝する気持ちを持たなければいけません。そして、「あなたがいてくれて、ありがとう」という気持ちを持たなければいけません。鴻池小学校にいる一人一人が大切な存在なのです。もしも、一人でも存在が否定されれば、それはいじめとなります。その行為は、人間として最も恥ずかしい行為であり、絶対に許されることではありません。
いじめをなくすためには、日頃から個に応じたわかりやすい授業を行うとともに、子どもたちが楽しく学びつつ、いきいきとした学校生活を送れるようにしていくことが重要です。子どもが生き生きと活動ができる学級経営の充実に向けては、「居場所づくり」にとどまることなく、認め合い、助け合う仲間づくり、「絆づくり」を進めていくことを通して集団の中で自分がどれだけ大切な存在であるか、自己有用感を高める取り組みが重要となってきます。その一つが、異学年交流です。「認めてもらえて嬉しかった」「役に立ててよかった」「自分ってまんざらでもないな」という自己有用感を高める取り組みは有効な手段の一つと考えます。相手の気持ちを推し量ることができる、優しい仲間が集う鴻池小学校をめざして、教職員と子どもとともにつくっていくことを誓い合いたいと思います。







更新日:2022年12月23日