令和4年4月【学校長の部屋】鴻池小
継続は力なり
令和4年4月28日(金曜)
新学期がスタートした4月、誰もが不安の中でスタートしています。教師にとって始業式からの3日間がいかに大切なことかは、誰もが知っていることです。1年間の学級経営を左右する大切な時期です。この3日間というのは、子どもにとって、新しい教室、新しい先生、新しい友だち、そして進級したという気持ちでもって、新しい自分に変わっていこうと心新たにスタートを切っています。いい意味で緊張感を持って過ごすときです。まずは学級経営の土台づくりが大切になります。子ども理解の基づく、信頼関係が、学級経営の土台となります。簡単なことです。子どもと目線を合わせて、話を笑顔で聞いて、ときに相槌を入れてあげれば、子どもは「先生はちゃんと私の話を聞いてくれている」という安心感が生まれます。この安心感が学級作りの土台です。
そして、3週間がたちました。人が何かを習慣化するのには約3週間かかり、それを超えたら、習慣がその人にとって欠かせないものになると。これを『マルツの法則』といい、アメリカの形成外科医のマックスウェル・マルツ博士の実験で明らかにしたものです。自分の学級をふり返るいい時期にきています。「先生が教室の前に立ったら話を聞く」、「チャイムがなったら席につく」、「あいさつをする」など、どんな小さなことでもしっかりと継続することで、習慣化されます。その一つ一つの積み重ねが学級経営のさらなる土台となります。始業式から3週間が過ぎた今、そういった小さいことができていたのか、できていなかったらどうすればいいのかをふり返る時期だと思います。文部省「小学校における基本的生活習慣の指導」(1985年)では、「習慣とは、学習によって後天的に得られる比較的恒常的な行動様式のことである。社会の慣習と密接に結び付いていると同時に、習慣化した行動様式は、それぞれの人格において現れてくる。基本的生活習慣は、特に人間が生活を営み、それを発展させるうえで、最も基本となるものである」と記載されています。長い連休に入ります。今一度、自分自身の学級経営をふり返ってみましょう。
Dream come true.
令和4年4月15日(金曜)
「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり」。この言葉は、江戸時代の米沢藩主だった上杉鷹山の言葉です。「どんなことでも強い意志を持ってやれば、必ず結果がでる」という意味です。簡単に「できない」と諦めることなく、「チャレンジ」することの大切さ、「やる気」の大切さを説いた言葉でもあります。
鷹山は、越後(新潟県)の米沢藩、戦国武将の上杉謙信を家祖とする大名の家柄です。謙信のあとを継いだ景勝は、豊臣秀吉の信任を受けて五大老の一人となり、秀吉の命で会津120万石へ転封となりましたが、徳川家康に敵対した関ヶ原合戦後の米澤30万石に減封されました。さらに、四代藩主綱勝が世継ぎのないまま急死してために、お家の断絶は免れたものの15万石に減封されることになります。上杉家は会津120万石の八分の一になり、九代藩主重定の時代には藩財政は破綻寸前の状況になりました。この窮乏の藩財政改革を見事に成し遂げたのが17歳で十代藩主となった鷹山です。鷹山が藩主となって読んだ歌「受け継ぎて国の司の身となれば 忘るまじきは民の父母」。国を受けついで藩主の身になったからには、自分は領民たちの父であり、母であるという決意を歌にしています。この思いを忘れずに質素倹約、学問の奨励、殖産興業に率先垂範で取り組み、必死の覚悟で一生をかけて藩復興にあたられます。
その鷹山を尊敬すると言われたのが、1961年、第35代アメリカ合衆国大統領に就任したジョン・F・ケネディです。ケネディは、旧ソ連との核戦争勃発の可能性のあったキューバ危機を救った指導者として有名ですが、就任時に記者会見に臨んだ席上で、日本人記者から「日本人で最も尊敬する政治家は誰ですか?」と質問をされ、「YOZAN UESUGI」と答えています。記者は、予想だにしなかった名前にビックリだったようです。ケネディは、鷹山の姿に、自分の理想とする政治家の姿を重ね合わせたのでしょう。
鷹山の「為せば成る」の精神が、藩財政は破綻寸前の状況にある米沢藩の窮地を救ったことになります。子どもたちも自分の夢に向かって、諦めないで行動することで夢が叶う、まさに「Dream come true.」です。
入学式より
令和4年4月11日(月曜)
春の訪れを感じられる8日(金曜)に、入学式を挙行いたしました。教職員一同、93名の新入生を迎えることができ本当にうれしく思っています。これで、新入生も鴻池小学校の仲間です。新入生の入学をお祝いして中川ひろたかさん作の「おめでとう おひさま」(小学館)を読みました。
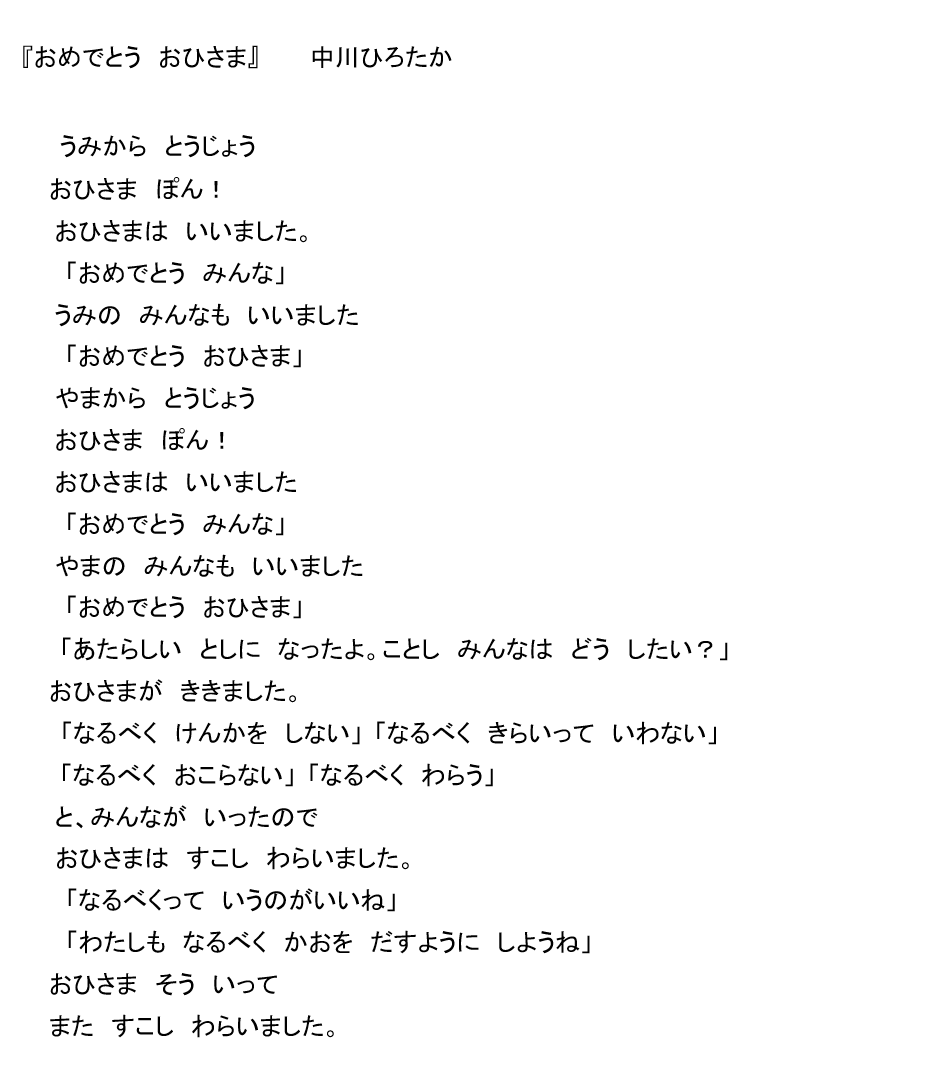
「おめでとう おひさま」の絵本の中にもあったように「なるべく」っていうのがいいですね。あわてず、少しずつ学校生活になれていってください。まずは、次の三つのこと、一つ目は、「気持ちのよい挨拶や返事をする」こと、二つ目は、「友だちと仲良くする」こと、三つ目は、「いろいろなことにチャレンジする」ことは、よく守って立派な鴻池小学校の1年生になりましょう。
保護者の皆様、お子様のご入学誠におめでとうございます。心よりお喜び申し上げます。人生の中で初めてという体験は数多くありますが、はじめて学校に行くという体験は、特別だと思います。私たち大人でも、知らない世界に行くことは、不安なものです。子どもにとって、初めての学校、期待と不安がいっぱいのはずです。「友だちができるかな」「勉強は大丈夫かな」「先生は優しいかな」「給食っておいしいのかな」、そんなドキドキわくわくの子どもたちを、ご家庭でも応援してあげてください。
本校では、今年度「ひとみ輝き 笑顔あふれる 鴻池小学校」を学校教育目標に、鴻池小学校のキャッチコピーを「失敗を恐れず『まずは、やってみよう』」としました。子どもたち一人ひとりがひとみを輝かせ、小学校生活をおくれるよう、そして、子どもたちの笑顔があふれるような学校になるよう教職員一丸となって、全力を挙げて取り組んで参ります。そのためには、何よりも、ご家庭と学校が手を携えて、同じ歩調でお子様の教育にあたることが最も大切なことだと思います。お子様のことで、ご心配なことやお悩みなどがございましたら、どんな小さなことでも結構ですから、決して遠慮されず相談しながら進めて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1年生の子どもたちが、元気に鴻池小学校に来ることを楽しみにしています。入学した93名の子どもたちが、すくすく成長することを祈念いたします。
始業式

令和4年4月7日(木曜)
進級、おめでとうございます。今日から新しい教室で、新しい学年がスタートします。新しいスタートは、これまでの自分を変えるチャンスです。どの子も、やる気に満ちあふれているのを感じます。その気持ちを大切にしてください。そして、1年を通して校長先生から2つのお願いがあります。
1つ目は、「まずは、やってみよう」ということです。これから始まる学校生活へ期待と不安でいっぱいのことでしょう。目標を決めて取り組んでみましょう。例えば、「勉強を頑張る」「挨拶をしっかりする」「早寝早起きをする」「先生の話をしっかり聞く」「発表を頑張る」など、どんな小さなことでも構いません。できればそれは自信につながります。目標を決めたら、「まずは、やってみる」です。
2つ目は、「笑顔あふれる学校にしよう」です。学校生活の中でたくさんの笑顔を作ってほしいと思います。勉強や運動に一生懸命に取り組んで「できた」とき「わかった」とき、笑顔が生まれます。先生からほめられたとき、うれしくて笑顔になります。友だちと仲良く過ごしているとき笑顔が生まれます。一人ひとりの笑顔は、たくさんの人の笑顔を誘います。そして、明るい挨拶ができる人は、優しい気持ちの表れです。優しい気持ちがいっぱいになれば、優しい気持ちをあいさつに代えて、あいさつがいっぱいになれば、友達へのいじわるも、悪口も、乱暴も、いじめもみんななくなって、みんなの笑顔があふれる学校になると思います。
皆さんのこれからの頑張りを全ての先生方が見ています。先生たちも笑顔のあふれる学校となるよう一緒に頑張っていきます。みんなですばらしい学校にしていきましょう。
新しいスタートにあたって
令和4年4月4日(月曜)
新しい先生たちを迎えて校内では令和4年度がスタートし、新学期に向けて準備が進められています。最初に先生方に「失敗を恐れることなく、『まずは、やってみよう』の精神で取り組んでいきましょう」と話をしました。先生方自身が自分に自信を持って取り組むことが、子どもたちにいい影響を与えるものです。子どもたちは先生の姿から学びます。教育学者ウイリアム・アーサー・ワードの言葉に「凡庸な教師はただしゃべる。よい教師は説明する。優れた教師は自らやってみせる。しかし偉大な教師は心に火をつける」とあります。この言葉のとおり、偉大な教師は子どもの心に火をともし、やる気にさせるのだということです。本校の大きな課題は、子どもたちに自信を持たせることです。自己有用感、自己肯定感など、子どもたちの自尊感情を高めることが大きな学校命題です。そのためには、子どもの心に火をつける教育活動が必須です。教えるだけの授業から考えさせる授業へと、授業転換を図る必要があります。先生の一方通行的な授業の時代ではありません。子どもの考えを支え、促す発問や指示を行う、いわゆるファシリテーターとしての役割も求められています。授業計画にあたっては、子どもにどのような力を身につけさせたいのか、そのための授業の目標は何か、目標に向けてどのように学ばせるのか、そして、振り返りでは、身についた学力を子ども自身に気づかせるメタ認知の場とならなければなりません。この取り組みは、きっと一人ひとりの子どもたちに自信を持たせ、達成感を味あわせることにつながるものと思っています。のっけから、授業改善の話をしましたが、やはり私たちは、授業で勝負するしかありません。授業が変われば子どもも変わります。重松清さんの「教育とはなんだ」(筑摩書房)の中で、国立情報学研究所社会共有知研究センターセンター長・教授の新井紀子さんは、教育のありかたについて、「『わからない』は悪いことじゃない。自分の世界を広げるきっかけになる経験だと思います。『わかる』ことは、『すぐにわかる』ときたときは浅い。『わからない』から『腹が立つ』、だから『考える』、そして『わかった!』となった方が深い」と。さらに、「『わかった!』から『自慢する』、でも『みんながわかってくれない』、『悔しい』、だから伝え方を『工夫する』、そしたら『みんなにわかってもらえた』と、何層に重なって『わかる』に至る」とも言われています。最も不幸なのは、「わからないことが、わからない」ことだとも言っています。
私たちは、鴻池というチームです。鴻池の子どもたちのために、チーム一丸となって対応を図ることが求められます。皆が同じベクトルで取り組むため些細なことでも自分一人で抱え込まないこと、「きょう、こんなことがありました」と気軽に教頭先生に話してください。「教頭先生が忙しそうだったので」ではなく、話を聞くことも教頭先生の仕事ですから。そうすることが鴻池小学校の信頼につながります。みなで情報を共有し、みなで解決を図っていきましょう。







更新日:2022年06月23日