令和3年11月【学校長の部屋】
音楽会を通して
令和3年11月24日(水曜)
11月20日(土曜)、Withコロナの状況のもと音楽会を開催することができました。3年ぶりの音楽会となったため、1・2・3年生にとっては初めての音楽会となりました。音楽会の大きな目的は、学年全員で音楽を創り上げることです。楽器が苦手な子も、音楽が好きでない子も、最後まで協力してやり遂げ、「やってよかった!」と思わせる達成感を味あわせることに意味があると思っています。そして、音楽を通して、努力することの大切さや、仲間と協力することの大切さを学びます。
今年度の音楽会では、合唱がないことに少しさみしさを感じますが、それぞれの発達段階に応じた合奏やボディーパーカッション、クラッピングなど、内容に工夫がありました。合奏も一人一人のよさや得意が生かされたものになっていて、練習の成果がわかりました。11月に入ってからは、毎日、体育館での練習が始まり、校長室にいると、子どもたちの演奏する音が心地よく響いてきていました。ついついその音に誘われて体育館に行くと、一生懸命に練習をしている子どもたちがいます。日に日に上手になっていくことがよくわかりました。はじめはバラバラの音が練習を重ねるごとに、重なり合って、響き合って、ハーモニーが生まれてくる様子が、子どもの力ってすごいなと感心させられることばかりでした。授業時間のみならず朝の時間や休み時間と時間を惜しんで練習をしている姿や友だちに声を掛け合って頑張って取り組んでいる姿も見ることができました。きっとご家庭でも夜遅くまで、鍵盤ハーモニカやリコーダー、中には、学校から持ち帰った楽器の練習に精を出した子どももいたかと思います。
音楽会の児童鑑賞日には、1年生から6年生までの児童が学団単位で発表し、互いに鑑賞し合いました。日常の授業で培われてきた成果を発表し、聴き合う授業の発展の場ともなりました。発表は各学年とも工夫を凝らしたものとなっていました。普段の授業では味わえない、各学年の子どもたちの心がひとつになって表現する場となりました。保護者鑑賞日にも、保護者の方にご来校いただき、子どもたちの練習の成果をご覧いただき、心一つに表現する子どもたちに温かい拍手を賜りました。一人一人の音や表現は、小さいけれども、心を合わせて一つの曲となって、ハーモニーを響かせていました。音楽会を通して、子どもたちの可能性と成長を感じることができました。
PTAの委員さんには受付や場内への誘導・整理等で大変お世話になりました。おかげさまで、無事音楽会を終えることができました。心よりお礼申し上げます。
アウトプットで子どもの力を伸ばす
令和3年11月17日(水曜)
学校では、能動的な学び、アクティブな学びが取り入れられ、子どもたちがアウトプットする機会が増えてきています。アウトプットとは、「話す」や「書く」など、自分のもっている情報を外に向けて表現することを言います。一方、インプットとは、様々な情報を入力することを言います。簡単に言えば、授業で先生の話を聞くこともインプットだし、教科書を読んで知識を得ることもインプットといいます。
様々な情報をインプットし、自分の考えをアウトプットしていくことが学びの一つのスタイルとなります。アウトプットの効果がよくわかる実験として、アメリカのパデュー大学のカーピック博士の実験が有名で、知識をアウトプットすることで長期にわたって記憶に残ることが検証されています。インプットばかりの学習になると、子どもたちは学習に面白さを失い、疲れてしまいます。見ただけになっていたり、聞いただけになっていたり、写しただけになっていたりする場合もあります。一方、アウトプットばかりでは、知識や経験に基づいた根拠のあるものでなくなることもあります。能動的な学びを大事にしなければならいことは言うまでもありませんが、アウトプットを目的にした授業を展開しなさいという意味ではありません。アウトプットはあくまでも学びのための手段です。インプットとアウトプットのバランスが大事になってきます。知識として得られた情報を確かなものとするために自分の言葉で表現、アウトプットさせてみることが大事です。よく授業中、ある子が発言したことに対して「同じです」という場面を見かけることがあるかと思いますが、その時「じゃ、今のことをもう一度説明してください」と返し、子ども自身の言葉で話させることもアウトプットと言えるでしょう。さらには、学習のふり返りもアウトプットにあたります。今日、学習してわかったことを客観的に捉え、次の学習へ生かすための改善点について、ノートに書いたり、発表したりすることで学びを確かなものとするからです。話を聞いてわかったつもりになっている場合がありますが本当に理解するとは、自分の言葉で表現できることだと思います。自分自身の言葉でアウトプットすることで、頭の中が整理されるなど、自分自身のことに気づき、新たな学びへと発展していきます。子どもが自ら学ぶような仕組みをつくっていくことが私たち教師の使命でもあります。
能動的な学びを
令和3年11月10日(水曜)
アメリカ国立訓練研究所の研究によると、7つの学習方法を学習の定着率を順番に並べた「ラーニングピラミッド」というものがあります。どの学習方法がしっかり頭に残るかを分類し、ピラミッド型にまとめたものです。単に講義を受けるだけでは、学習定着率が5%と低く、覚えたことを他の人に教えると学習定着率が90%になります。ラーニングピラミッドが表す数値が正しいか否かは別にして「グループ討論」「自ら体験する」「他の人に教える」といったアクティブ・ラーニングが、学習の定着率が高いと言えるでしょう。つまり、受動的な環境ではなく、能動的になる環境が効果的だということになります。アクティブ・ラーニングとは、教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学習者の能動的な学習への参加を取り入れた教授・学習法をいいます。学習者が能動的に学習することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図ります。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれますが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法です。

鴻池小学校では、子どもが見通しをもって、主体的に取り組める「課題設定の工夫」、そして、自らの考えを広げたり、深めたりする「話し合い活動」、さらには、学んだことをふり返り、次時の学習につなげたり、生活に生かしたりと「ふり返り活動の充実」を共通実践項目として、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善に努めています。
授業中、子どもたちに「わかりましたか?」と聞けば必ずと言っていいほど「はい」と返事をしてきます。このような学習スタイルではいつまでたっても、子どもの学力を伸ばすことはできません。まずは、課題を工夫することで、子どもの意欲をかき立て、めざすゴールを明確し、見通しをもって学習させることです。そして、その学びが確かなものとなるよう考えを交流させることです。そのためには、その土台となる学級づくりが大切になります。子どもたち自身が高め合う場となります。学習が楽しくなれば、次に何をしたいか、何に生かしたいか自ずと出てきます。まだまだこれから、学びが楽しいものとなるよう努めていきましょう。
人との出会い
令和3年11月1日(月曜)
この10月18日に84才で亡くなられたアメリカで黒人として初めて国務長官を務めたコリン・パウエル氏の「13カ条のルール」の記事が神戸新聞に載っていました。「13カ条のルール」とは、パウエル氏が残した自らを戒める13枚のメモのことです。「13カ条のルール」に、少し興味が引かれ、パウエル氏著書の「リーダーを目指す人の心得」(飛鳥新社)を読んでみました。この著書は、パウエル氏自身がこれまで出会った人々、家族、友だち、同僚、上司、部下、好敵手などの話をメモしてきたものです。人生やリーダーシップについて教えてくれる一冊です。本書の最後に、「人生とは、様々な出来事の連続。人生とは挑戦し、乗り越えた困難、乗り越えられなかった困難を意味する。人生とは成功と失敗の連続、これらの全てをあわせたよりも大きいのが、出会った人々とどのように触れあったのか、人生は全て人なのだ」と締めくくっているところが印象的でした。相田みつをさんの詩の中にも人との出会いをテーマにした「その時の出逢いが」という詩があります。尊い人との出会いと感動が人を大きく成長させてくれる。そのように私は感じています。
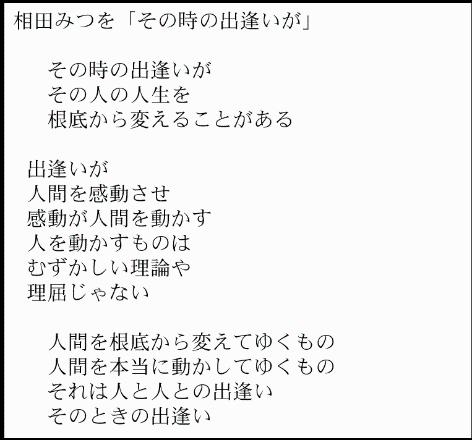
私たちは、生まれてからこれまで多くの人と出会い、そして、これからも多くの人と出会うこととなります。この一つ一つの出会いが、自分の生き方やこれからの人生の方向を決めてきたように思います。今、私がこうして教職の道に入ったのも大学時代の恩師との出会いがあったからこそだと感じています。この出会いが私の人生を決定づけたと言っても過言ではありません。出会いによって、人は変わります。生き方が変わります。広い世界の中で、家族と出会い、仲間と出会い、信頼できる人と出会うことの一つ一つの何気ない出来事が奇跡だと思っています。そして、自分自身も人の生き方に影響を与えられるような人間になっているのか、自問することがあります。ただただ、今ある私は出会った人に感謝です。







更新日:2021年11月24日